
活動報告
大ケヤキの思いを郷土史機関誌にも
2023年5月16日 | 大ケヤキ
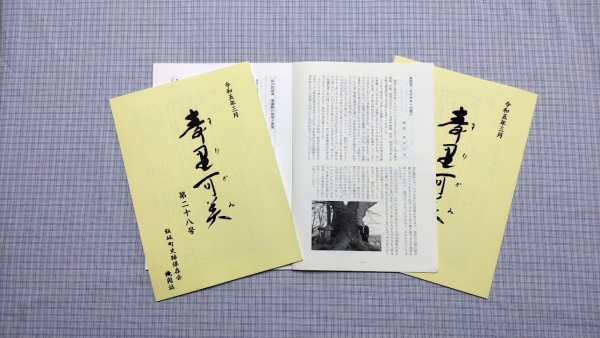
福島市飯坂町の史跡等文化財の調査、研究、保存を目的とした飯坂町史跡保存会の機関誌・寿里可美(すりかみ)の第28号に巻頭言を書かせていただきました。タイトルは「大ケヤキへの思い」。これまでホームページで報告している樹齢350年の巨木・古舘の大ケヤキの令和4年4月からの保存活動をまとめました。
機関誌は前62ページ、会員の投稿や地域で行われた伝承後援会の記録、保存会の研修旅行や年表発刊など事業報告などをまとめています。
巻頭言は以下の通りです
「大ケヤキへの思い」
歴史に興味を持ったのはいつごろだっただろうか。古代文明や遺跡、史跡、恐竜の化石そして美術や建築、哲学、科学など多くの分野で歴史的なことに関心を持ってきました。
その中で最近は「自然」を意識しています。きっかけは地元平野の樹齢350年の巨木・古舘の大ケヤキとの出会いでした。ちょうど2年前、太い幹に割れが生じ、このままでは倒木してしまうのではないかという事態が起きました。市の文化財でもあり、地元の方々がしかるべき部署に対応を要望しましたが、かなり高額な費用の半分を地元が負担としなければならないという説明でした。その後、事態は深刻さを増し、令和4年には切り倒さなければならないというところまで来てしまったのです。
350年も生きてきた高さ約30㍍、根回り約16㍍の巨木を我々の時代に切り倒していいのかとの思いから地元の方々と話したところ「何か方法があれば切りたくない」「残せるなら残したい」という本音を聞かせていただきました。知り合いの県議を通じ県に問い合わせたところ、県の森林環境交付金を活用できることが分かり、保存の道が開けたのです。
大ケヤキが植えられたのは1670年前後、飯坂町史跡保存会が発行した「飯坂町歴史年表」によれば、平野地区は米沢藩領から幕府領になった時期ではないかと思われます。立っているところは土塁の上で、すぐそばには空堀もあります。地名の古舘の舘が舘(やかた)であるとすれば、どのような人物の舘でどんな役割を持っていたのか、舘はどこにあったのかなど、分からないことばかりです。
それから350年、江戸から令和の世までこの木は地域の歩みを見てきたのだと思います。そして多くの人が大ケヤキをご神木として敬い、慕い、守ってきたのだろうと思います。その思いがこの木には宿っているのではないでしょうか。この木を守り、後世に伝えていくことは今に生きる私たちの責任ではないかと思っています。私たちの都合で大ケヤキを歴史のページから切り取ってしまうことはできません。この木を次の世代へ、さらにその次へとつないでいかなければなりません。今後も大きな関心を寄せ、この木を守り次の世代へつないでいきたいと思っています。